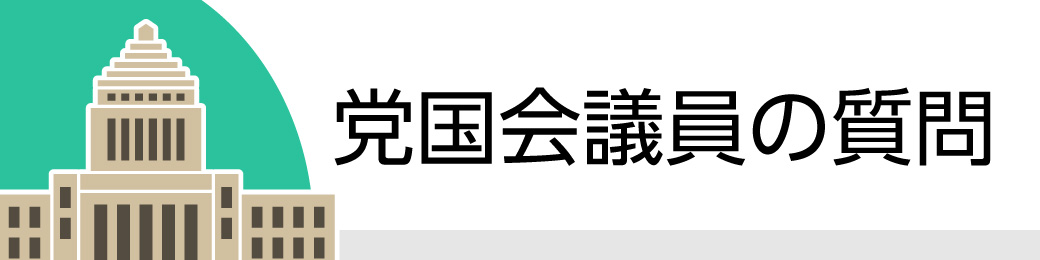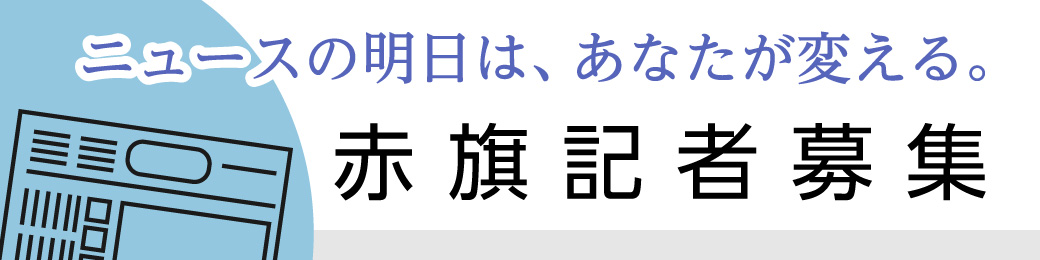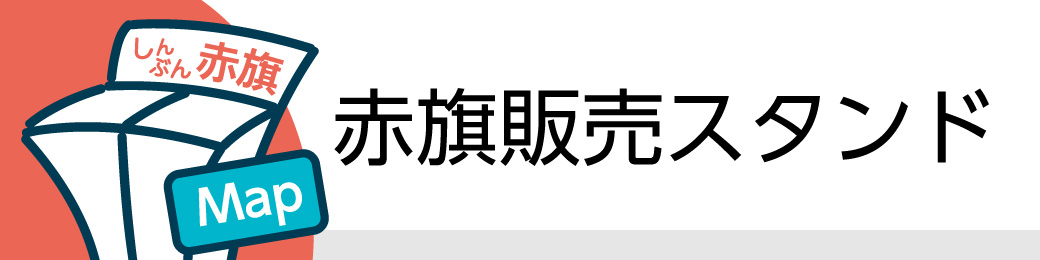2025年3月29日(土)
屋内退避 継続判断は3日後
規制委検討チーム報告書
「一時外出は必要」明記
原発事故時に被ばくを低減するために行う屋内退避の運用について原子力規制委員会の検討チームは28日、報告書をまとめました。屋内退避開始から3日後を退避の継続を判断する最初のタイミングの目安とし、その後も退避継続が基本としています。近く規制委に報告され、原子力災害対策指針(原災指針)への反映などを検討します。
報告書は原発事故と自然災害が同時に起きる複合災害について、「自然災害対応との連携を強化することが極めて重要」との記載にとどまっています。しかし、2月の意見照会で43自治体から寄せられた約250件の意見の中には、「(複合災害の前提なしに)避難計画の実効性が図れない」と、複合災害時の対応の具体化を求める意見が複数ありました。
原災指針では、事故が発生し周辺住民に放射線の影響の恐れがある場合は、原発から5キロ圏内(PAZ)の住民は避難を実施。5~30キロ圏内(UPZ)の住民は屋内退避し、その後、空間放射線の測定結果に応じて避難などに移行することになっています。
しかし、昨年1月の能登半島地震では、断水や家屋の倒壊、避難道路の寸断、一部の放射線防護施設が損傷。同県にある北陸電力志賀原発は運転停止中でしたが、仮に事故が起きていれば多くの住民が屋内退避も避難も困難な状態でした。
規制委は、原災指針の考え方を変更する必要はないとした上で、屋内退避の実施期間などについて検討チームで昨年4月から議論。
報告書は、屋内退避実施3日後も、プルーム(放射能雲)対策が必要な場合は、屋内退避の継続を基本として、継続可能かどうかを日々判断。生活の維持が難しいと判断されれば、国が地域ごとに避難への切り替えを判断し、指示することが適切としています。一時的な外出も退避の継続上、必要な行為と明記しています。