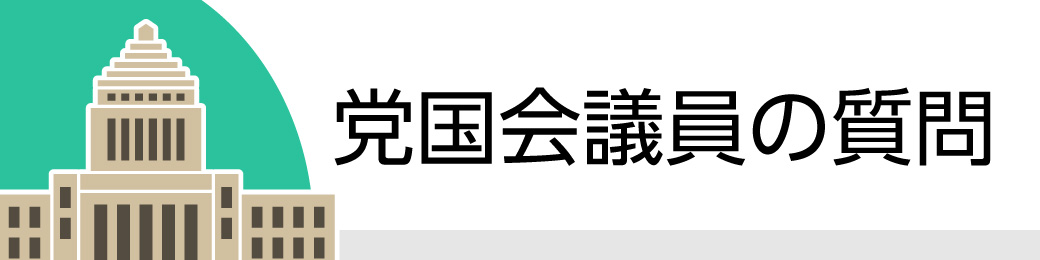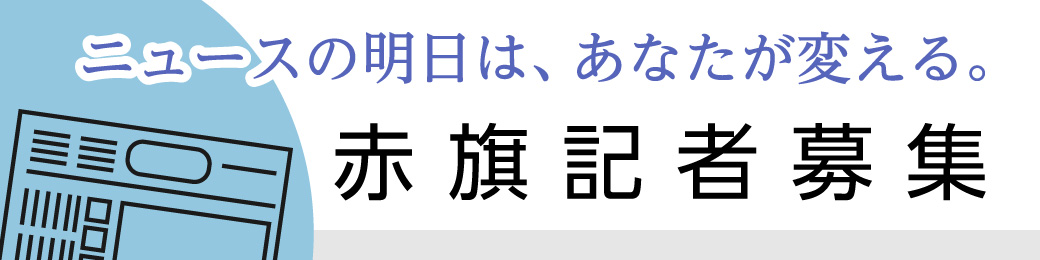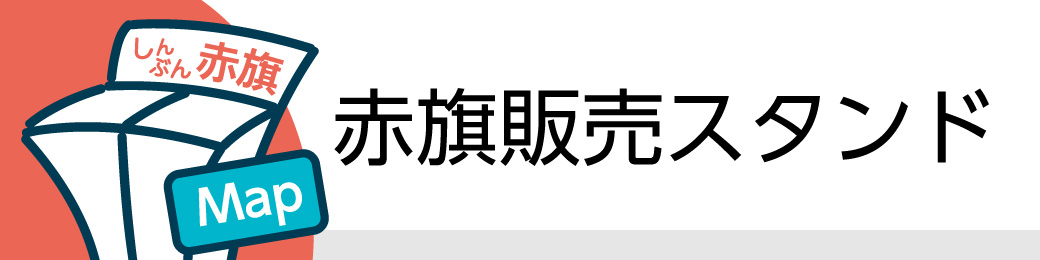2025年3月30日(日)
解説ワイド
教員の働き方を考える
国が長時間労働つくる
教員の労働条件は子どもの教育条件
教員の長時間労働がとまりません。過酷な働き方に志望者は減り、このままでは学校がもたないところまできています。この事態に、政府はわずかな賃上げと引き換えに“定額働かせ放題”を放置する法案を出し、日本共産党は政策「このままでは学校がもたない」(1月30日)で厳しく批判しました。あらためて教員の働き方について考えます。(日本共産党文教委員会責任者 藤森 毅)
残業代ゼロの青天井
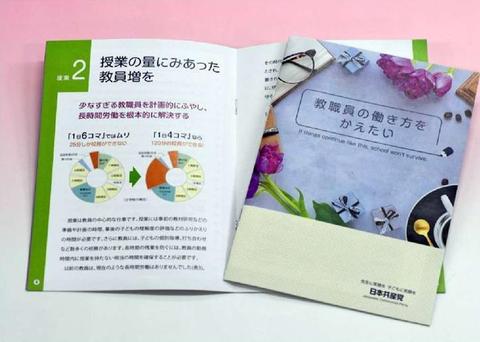 (写真)日本共産党が1月30日に発表した政策「このままでは学校がもたない―『教員残業代ゼロ制度』の廃止、授業にみあった教員定数を」を紹介するパンフ。A5判カラー16ページ。問い合わせはお近くの都道府県委員会、地区委員会まで |
教員の労働時間は、じつは授業に大きく左右されます。
たとえば小学校で1日に6コマの授業をこなし、法律通り休憩をとると、定時退勤まで20分しかありません。授業の準備、採点、子どもの個別指導、書類書き等々が終わるはずもなく、残業は必至です。逆に1日3コマとなれば、7時間労働の展望がみえてきます。
教員1人あたりの授業負担の標準は、国の法制度で決まります。授業の総量は国の学習指導要領でほぼ決まり、それを受け持つ教員数は義務教育標準法という法律で決まるからです。
1966年の教員の残業は小学校で1日16分、中学で30分と、今の10分の1以下でした。当時の義務教育標準法で、小学校を例にとると教員1人あたりの授業が「1日4コマ」となるよう、教員定数を調整していたためです。ところが、今は「1日5コマ、6コマ」が当たり前。国が必要な標準法の調整を怠った結果です。小中学校の勤務日の平均労働時間は、11時間を超えます。
労働の世界には、長時間労働になった時のブレーキがあります。労働基準法にある残業代制度です。残業に25%増、あるいは50%増の賃金支給を命じるこの制度は、雇用主のコスト意識に訴え長時間労働を抑制する、世界共通のルールです。教員の残業は年9000億円分と推定され、それより教員をふやし残業をなくす方がはるかに経済的です。
ところが、公立学校の教員だけ、公立教員給与特別措置法(給特法、1971年)という法律で、このブレーキが外され、残業代ゼロなのです。法制定当時、公明党をふくむ全野党が「労働時間が青天井になる」と猛反対しました。その指摘はまさに的中しました。
「1日8時間労働」(労働基準法)は国が守るべき大原則です。その国が、別の法律で過労死ラインの長時間労働をつくる異常。しかも、それを改めることを拒否する異常。この不正義は必ず正されるべきです。
教員の労働条件は子どもの教育条件です。授業準備の時間がなく深い授業ができない。いじめかな?と気になっても踏み込む時間がない…。教員の長時間労働は、個々の教員の努力を超え、教育を貧しい方向へ押し流す、深刻な問題です。
自由奪われ心通わず
 党は教職員向けアンケートも実施中。回答はQRコードから |
教員の働き方にはもう一つ、教育者としての自由の問題があります。
「どんな社会のもとでも、教師は子どもとともに生きてきた」―戦後教育学をリードした勝田守一の言葉です。教員は子どもを愛し、守るために多少の犠牲をいといません。そのためには適切な労働条件とともに、自分で判断して仕事をすすめる、専門職としての自由が必要です。
ざわついた学級の状況を見て取り「次の授業は外遊びにしよう」と決断できる自由がかつてはありました。自由こそ教員と子どもが心を通わせる土壌です。子どもを育てられるのは、機械ではない自由な人間なのです。
ところが、その自由の余地が年々狭まっています。
授業は「学習指導要領通り」で、同一の進度を求められ、はては板書の仕方の統一を求める動きもあります。子どもを細かいルールで点検する学校もふえました。「靴箱の靴のかかとを何センチ以内にそろえる」といった類いです。子どもと心が通わなくなることをさせられる教員は、心が折れます。
この背景には、指導要領の強制、職員会議の形骸化、全国学力テスト、教員評価制度、官製研修の強化など競争と管理の政策の堆積があります。政府はそれでも足りないと、法案に「主務教諭」の導入を加えました。教員を上下にわけ、上意下達の学校運営を強めるものです。しかし、いま必要なのは「主務教諭」でなく、自由な話し合いができる職員室のはずです。
苦しみの根本は同じ
 (写真)北海道高等学校教職員組合にパンフを届けて懇談する(左から)日本共産党の宮内しおり北海道選挙区予定候補、はたやま和也参院比例予定候補=3月13日、札幌市内 |
こうして今、教員は長時間労働と自由の剥奪という危機の直面しています。その源はすでに見てきたとおりの政治です。
その土台には、巨大資本が社会を好き勝手にしてもうける自由を追求する、新自由主義があります。市場原理・効率化の名による予算の削減、管理者が目標を決め、その達成度で人々を評価する組織マネジメント…。公教育は攻撃にさらされ、萎縮しています。
当然、国民も無傷でいられません。労働者は尊厳ある個人でなくコストとして扱われ、法律が変えられ雇用環境は激変しました。格差は拡大し、人間関係が奪われ、それでも人は少しでもいいポジションへと、展望のない競争に加わらざるをえません。
ここに親の苦悩があり、子どものストレスがあります。それは時に教員を攻撃しますが、教員の苦しみと根は一つです。子どもの不登校の急増と教員のメンタルによる病休の急増が、メダルの表裏のように。
あり方を変えよう
「このままでは学校がもたない」とまで言われる教員の危機の打開は、当事者とその周りにいる人々の切なる願いです。誰もがこのままでいいと思っていません。
そのための道筋が示される必要があります。日本共産党が政策をパンフ(写真)にしたのは、解決策は政府の法案にはなく、教員増と残業代制度適用にあることを、軍拡でなく教育予算の拡大が必要なことを、多くの人々と語り合う必要を痛感しているからです。そして、子どもも教員もつまらないと感じるような学校のあり方も変えていこう、と。この方向を一貫してすすめ、山を動かしたいと思います。