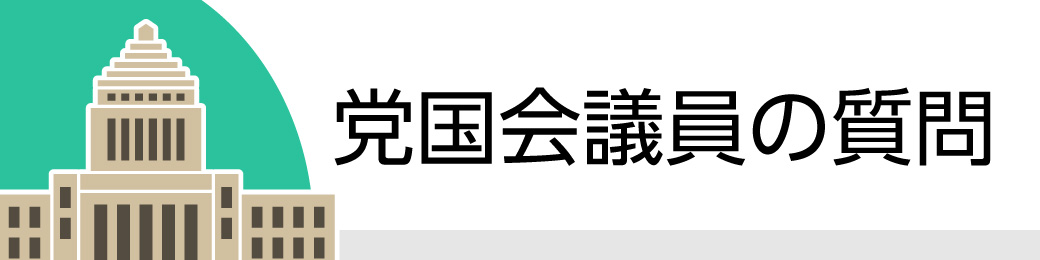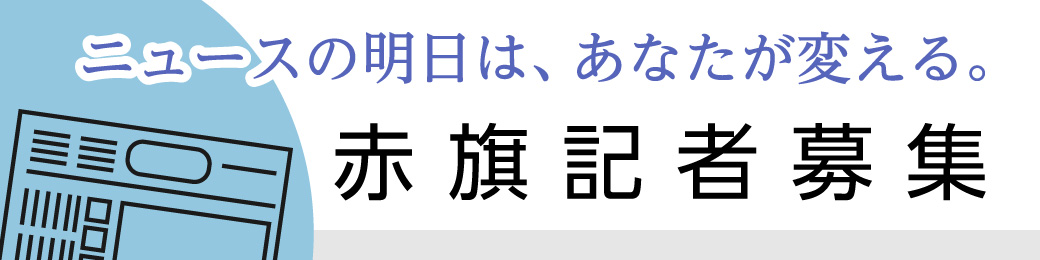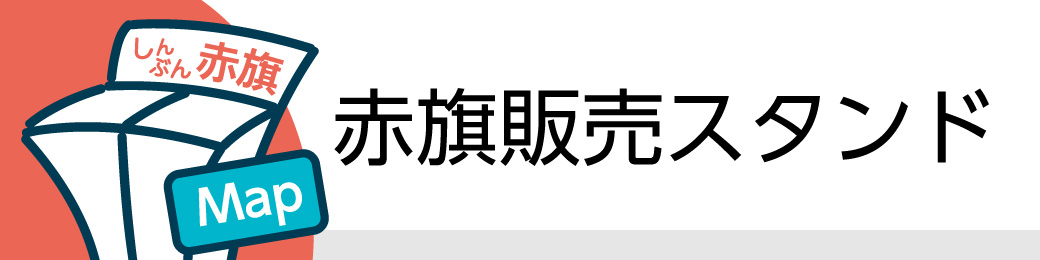2025年4月19日(土)
2025とくほう・特報
シリーズ 介護保険25年
訪問介護報酬引き下げ1年
長時間・過密労働 現場は悲鳴
自公政権が訪問介護報酬を2~3%引き下げ4月で1年。引き下げ後、6割の事業所が減収になったことが厚生労働省調査で明らかになっています。一方、減収を免れた事業所は訪問回数を増やしていました。しかしホームヘルパーは有効求人倍率14倍の人手不足。限られた人材が長時間・過密労働にさらされています。都市部では1日8、9軒の訪問も。「これでは続けられない」。不安の声が上がります。今月上旬の日曜日、京都市でヘルパーに1日、密着しました。
 (写真)75歳の男性宅で朝の服薬確認=午前8時過ぎ、京都市内 |
1軒目。午前7時57分、小雨のなか、上京区のワンルームマンションにヘルパーステーションわをん、で管理者を務める成松美由紀さん(60)が現れました。今日は1日9軒の訪問が予定されています。昨夏まで日曜日は4軒でしたが、倍以上に増えました。
「朝ご飯食べましたか?」。待っていたのは75歳の1人暮らし男性。精神疾患とパーキンソン病を患い、手足が不自由です。小刻みに震える手に薬を渡します。ヘルパーが訪問して服薬を確認しないと、飲み忘れが起きます。
便と尿で汚れた紙パンツを脱がし、尻を拭いてはき替えを手伝います。歯磨きと洗顔が終わるとベッドに横になってひげそり。電子レンジで蒸しタオルを作り顔へ。男性は「ちょっと熱い」。照れくさそうに声を上げました。
「ヘルパーさんは真面目。いなかったら、どうしたらいいか分からない」と男性。「もうちょっと長くいてくれたらなぁ」。朝の援助は身体介護で30分、食事作りがある夜は生活援助が加わりますが、60分で終わりです。
トイレの壁も拭きます。「ふらつきで尿があちこちに飛んで、においがきつかったんです」。いまはまったく臭いません。冷蔵庫をあけ食料をチェック。ヘルパーが炊き、小分け冷凍したご飯が8個あるのを確認。「今日は炊かなくてもいいね」。値上がりした配食弁当は払いきれなくなり、冷凍食品とヘルパーの簡単な調理で節約しています。男性の様子を他の介護事業所と共有する連絡帳に記入を終え、退室しました。
ヘルパーいつまで続けられるか
電動自転車で移動短縮
 |
8時半前、雨が本降りに。雨具を翻し電動自転車で次へ急ぎます。2・7キロ15分の予定を10分に短縮。5分早く支援にはいりました。
2軒目。6畳一間のアパートに知的障害のある女性(76)が1人で暮らしています。糖尿病で服薬確認が欠かせません。紙パンツを交換して陰部を洗浄。居室を掃除し、翌日のデイサービスの準備をすると30分で終了です。
この女性は昨年夏まで、障害者サービスを利用して日曜日に成松さんと買い物に行くのを楽しみにしていました。ところが件数が増え中止に。「今日はこれで終わりよ」と成松さん。女性は「わかってる」。寂しそうでした。
路地を疾走して3軒目へ。坂道で記者はついていけなくなりました。目的地付近で合流すると、成松さんはその間にスーパーでトイレを借りて用を足していました。
3軒目は元酒店の京町家。95歳の女性が居間の介護ベッドで横になっています。心臓病があり、圧迫骨折を繰り返しています。同居の息子は夜勤明けで寝ています。おむつを交換、ホットタオルで顔を拭いてもらう間に成松さんは朝食の準備。ご飯を解凍しておかゆをつくり、玉子スープとしば漬けを添えます。栄養補助食品も。食後は口腔(こうくう)ケア。ベッド脇のポータブルトイレの汚物を処理します。
「下の世話をしてくださってねぇ、ありがたい。この方とは気が合うんです。(ヘルパーの)なり手が少ないというのは困ります」。台所や洗面所は土間にあり居室との間には数十センチの段差が。1時間で10回近く上り下りするのは、大きな負担です。
雨が上がると蒸し暑くなりました。信号のない路地を選び、駆け抜けます。
 (写真)雨具を被り自転車で出発=午前11時半過ぎ、京都市内 |
4軒目は69歳の女性が1人で暮らすアパート。脳梗塞の後遺症で半身まひと高次機能障害があります。「どうですか? お好きなコーヒーいれますね」。成松さんは息が切れ、肩で息をしていますが優しく声をかけます。食器を洗いながら連絡帳に目を通します。冷蔵庫から材料を出して切り、昼食の炒め物を作ります。終わるとラップして掃除へ。優先順位の高い作業から済ませていきます。一瞬も止まることなく動き続け、食事をベッドサイドに運び介助。女性は小さな声で「おいしい」。笑みがこぼれました。
5軒目は早朝と同じ男性のマンションに戻り、障害者サービスで中華料理店へ同行支援。成松さんは1時間後、やっと昼休憩に入りました。
6軒目。午後一番は80代の夫婦と弟が3人で暮らす民家です。2階のベッドに横たわる弟(80)は抗がん剤治療中。「朝から何も食べてない」。検温すると熱があり、経口補水液をすすめます。血圧は正常値でした。「大丈夫」。男性の安心した様子を確認すると、成松さんは買い物に飛び出しました。
 (写真)訪問先の女性を助けて調理をする成松さん(左)=午後2時過ぎ、京都市内 |
5分でちらしずしなどの買い物を済ませ、戻ると調理にとりかかりました。ほうれん草をゆで、ごま和えの味付けは認知症の妻(81)に頼みます。「これでいけると思う」。味を整える妻の目がキラッと光りました。自信ありげです。成松さんはみそ汁、ちくわの炒め物を手早く作り配膳。「この人(成松さん)、仕事が早いのよ」という妻は「おらんようになったら? ものすごくこまるわ」と顔を曇らせました。買い物の精算を済ませトイレ掃除をすると、予定の60分を10分近くオーバーしていました。
7軒目は70代の男性障害者。団地の廊下を部屋へ急ぐ成松さんは、片足を引きずっていました。8軒目は69歳の女性宅への再訪。安売りスーパーに寄って買い物し、夕食と翌日の朝食を準備しました。物価高をしのぐため1パック一〇〇円のポテトサラダの半額セールをねらいます。
 (写真)利用者を訪問する前にスーパーで買い物=午後4時15分過ぎ、京都市内 |
9軒目は最初に訪問した男性宅へ。リンゴなど食品を購入して向かいます。リクエストに応じてリンゴをむき調理。服薬確認もあり1日3回の支援が必須です。
すべての訪問を終えた午後6時半すぎ。成松さんは疲労の色が濃く声も絶え絶えです。「疲れました。短時間・過密スケジュールでは利用者さんと十分コミュニケーションできないのが不安です」。肩や背中、股関節が痛み、この日は痛み止めを飲んでようやく眠れたといいます。翌日も痛み止めを飲み続け5軒訪問しました。「利用者に寄り添って支援し、元気になり喜んでもらえるので頑張ろうと思うし、この仕事は好きです。でもいつまで続けられるか分からない」と成松さん。
稼働率上げ過酷な状態
 (写真)櫻庭葉子さん |
ヘルパーステーションを経営する一般社団法人「和音ねっと」代表の櫻庭葉子さんは「われながらこれは過酷だと思いました」。ショックを隠しません。
同事業所は常勤職員4人と非常勤が4人の零細です。前年度は赤字。昨年4月の報酬引き下げで経営危機に直面しました。「カバーするには稼働率を上げるしかない」。みなで話し合い、訪問件数を増やすことにしました。その効果で24年度の訪問回数は前年の1・16倍に。前年比増収で赤字を脱却しましたが、持続可能性が問われます。
「利用者は重度化し、1日複数の訪問がないと生活できない方が増えています。でもヘルパー不足で他の事業所は受けてくれません。ヘルパーの平均賃金は全産業平均より月7万円低く、募集しても来ません。新規の依頼はすべて断っても、これだけ過密になっている。報酬引き下げは撤回してほしい」と櫻庭さん。
実はこの日、9軒の中には臨時が1軒含まれていました。近隣の事業所のヘルパーが3月末で1人離職し、代わりに行く人がおらず「わをん」に依頼してきたのです。同事業所の関係者は、「身体介護の時給を2000円に上げても応募はありませんでした。フランチャイズの事業所で、オーナーは5月に閉鎖、売却する意向です。譲渡先もおそらくヘルパー不足。約30人の利用者全員をみきれないと思います」と語ります。
「大手銀行の初任給が月30万円と聞き、自分の仕事は何だろうと思いました。サウナ状態での入浴介助。猛暑も雪も変わりなく戸外を訪問。介護報酬を決める政府の人は現場を見て、と言いたい」
(内藤真己子)
報酬削減の撤回求める
共産党が提言
報酬引き下げから1年。2024年度の訪問介護事業者の倒産は前年度比21・1%増の86件で、過去最多を記録しました。全介護事業所の倒産179件の48%を占めます。訪問介護事業所ゼロの自治体は引き下げ後、本紙調査で10増え107に広がりました。
報酬削減の撤回等を求める地方議会の意見書は、16道県議会を含む289に広がっています(中央社会保障推進協議会集計、3月末)。14日の厚労省・社会保障審議会介護給付費分科会でも、訪問介護の危機を懸念する声が相次ぎ、全国市長会代表が「国による事業者への直接的な財政支援」の緊急措置を要請するなどしています。
日本共産党は16日、「物価高騰から暮らしを守る緊急提案」を発表しました。削減した訪問介護報酬をただちに復活(国費50億円)し、介護保険の国庫負担を10%引き上げて、介護職員の賃上げと労働条件の改善、事業所の経営再建、介護事業が「消滅」危機にある自治体における事業継続への公的支援、などを提言しています。